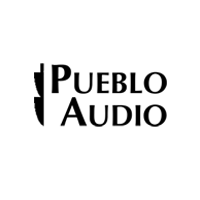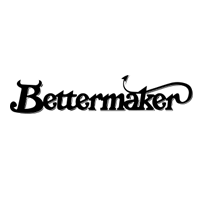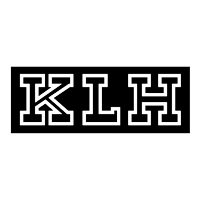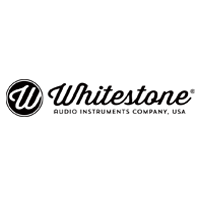LEARN - Nadine
進撃のコントラバス
ベーシスト / 作曲家・編曲家 川村竜
JAZZ, ELECTRO, J-POPを縦横無尽に活躍する若きトップ・コントラバスプレーヤー、川村竜氏は、コントラバス用マイクロフォン、Nadineユーザーです。国際コントラバスフェスティバルを日本人初、史上最年少にて最優秀賞を受賞するという輝かしい経歴を持つ他、プレーヤーのみならず、作編曲家としても常に規格外の活動を積み重ねています。オリジナリティーあふれるユニークなキャリアとコントラバスのサウンドについて伺いました。
エレキベースで17歳の時からお仕事をいただいています。中高校生の頃、プロになるならプロのベーシストに付いて学んだ方がよいと薦められて、とあるベーシストのライブに行きました。その時のドラムを叩いていた岩瀬立飛さんに目が行ってしまって、そのままベースではなくドラムのローディーを始めたんです。ベーシストのローディーをするとその人しか観れないですが、ドラムのローディーをするといろんなベーシストが観れるな、という悪ガキならではの策略もありました。(笑)中高生の頃から入ったのでいろいろコネクションがあって、演歌のリハーサルのトラをやったのが一番最初の仕事です。それからはいろんな仕事をいただくようになりましたね。運もよかったと思います。運はとても大事なんですよ。
二十歳の時、半年ほど音楽大学に通っていて、納浩一さんに、ジャズ、ウッドベースやらないの?両方弾けたら収入が2倍になるよ、と言われて始めました(笑)。当時の僕は全く知識がなくて、エディ・ゴメスや、マーク・ジョンソンの音をフレットレスベースかと思って聴いていたくらい、本当に右も左もわからなかった。納さんが、マイルス・デイビスのCDとかを貸してくれたんですが、当時の僕は相当ひねくれていましたから、一小節に音が4つしか入っていないので面白くないです、って返したら、こいつはダメだなあという顔をされまして(笑)。でも実際は、ボブ・ハーストや、チャールズ・ミンガスが好きでしたし、興味あるものにはとことんいく性格ですから半年の間に集中してジャズ理論を頭に入れて、そのあとの経験で合わせこんで学んでいきました。音大も、学生より講師陣と仕事するようになったので、ここにいてもしょうがないと辞めてしまったんです。納さんからは、君がプロなったのは納得いかないなぁ〜と言われました(笑)
僕がちょうど音大の在学中にダナ・ハンチャードというシンガーが短期間招聘されていて、仲良くなって彼女のバンドで演奏していました。彼女の旦那さんがニューヨーク・フィルの首席コントラバス奏者ということで、その彼からコントラバスフィスティバルというものが2年に一度、アメリカで開催されているので出てみないか、と薦められたんです。
毎回違う場所で開催されているものですが、2004年に行われたその時の開催地はハワイでした。本当にいろんな面白いコントラバス奏者が出場していました。15、16歳で参加してる子なんかは、もうめちゃくちゃ上手いし、インドから参加している人は、コントラバスにE弦に共鳴するシタール埋め込んでいました。それEマイナーの曲しかできないじゃん、バカだなあ、なんて(笑)でもそれがすごく好きで。当時は、ほとんどみたことのなかった5弦の人もたくさんいました。コンテストは、クラシックとジャズに分かれていて、その面白いプレーヤー達というのは、みんなクラシックの出場者達でした。僕はジャズでの出場でしたが、どちらかというとジャズの参加者達の方がスタイルに凝り固まっていた。
実はその当時、英語がよくわからなくて、僕は現地にバンドが用意してあると思ってひとり行ったんです。実際は、デュオならデュオ、トリオならトリオのメンバーを連れていかなければいけなかった。開催期間の一週間、ぶっ飛んだコントラバスプレーヤー達と過ごしたことで、“細かいことはもういいや”って何か吹っ切れて、コンテストはソロで臨みました。日本人らしいトラディショナルな曲、”さくらさくら”で始めて、ジャズの語法を使いながら広げて最後はフリーで終わる。その結果はスタンディングオベーションで最優秀賞を受賞。デュオ、トリオでジャズを一生懸命練習してきた人たちからすると、“ずるい”と思われたかもしれないですけど、その人達は運がなかったですね(笑)。その後、審査員にいた、ニールス・ペデルセンや、ジョン・クレイトン達とベース4台でアメリカ・ツアーに行きました。すごいコネクションだし、ありがたいし、とても楽しくて。クリスチャン・マクブライドとかも見に来てくれましたし、ボブ・ハーストとも仲良くなり今では僕の先生です。
そのフィスティバルでひとつエピソードがありました。日本では、弓の使い方はジャーマン式で教えています。それはメリットで選んでいるのでなく、最初にそのメソッドで日本に入ってきたからで、まだまだフレンチ式の人というのは少ない。50人くらいいたそのコンテストの出場者は、全員フレンチ式で、ジャーマン式は僕ひとりだけだったんです。フランソワ・ラバトというフランス人の生きる伝説的な奏者がいて、いかにジャーマン式がダメかという説明をするために、その50人の前でお前弾いてみろって、ステージに上げられたんです(笑)。だいぶ気分悪かったですけど、その日から僕もフレンチ式に変えてしまいました。
もともと僕自身は日本でも垢抜けたタイプと思っていましたけど、そのコンテストで完全に常識が壊れてしまいました。非常に良い経験でしたし、心からコントラバスっていいなって思うようにもなりました。本当にどこになんのチャンス転がっているかわからないんですよ。

ジャズ・ベーシストとして、日野皓正さん、ケイ赤城さん、辛島文雄さん・・・、本当に日本のジャズシーンを支えてきた昭和の方々と毎日ケンカしながら、たくさん学ばせていただいていた一方、昔のジャズは良かったという話は、やはり多いんです。ジャズ・バブルじゃないですけど、昔はこれだけもらえた、これだけ美味しいことがあった・・・。もちろん彼らが日本のジャズの土台を作ってくれたというリスペクトは一生忘れないですけど、その畑で収穫できるものがこの先もあるのか?そこを僕らが食い散らかしてもしょうがないんじゃないか?ということを考えさせられました。僕は、世代的にも今のシーンとのギャップがよく見えるポジションだったので、先々ずっとウッドベースだけをやっててもダメだなあ、作編曲、制作にシフトしていかなければと、思って昔から着々準備をしていました。
ベースシストは使う楽器の特性上、プロデューサーに踏み込みやすいですけど、ベースに捧げた時間と同じくらいを制作に捧げないと、アビリティーとクオリティーの両立は難しい。そこは自分のキャパシティもわかっているし、エンジニア、機材、トラック制作には、逆立ちしてもかなわない人というのはいるので、自分の得意なこと以外を全て任せられるチームをこのスタジオに構えるようにしました。エンジニア的なことも含めた音響を全て任せている作曲家でDJのZANIOと、もうひとり映像関連に強い、トータルアドバイザー的な、はたまたフィクサー的な(笑)スタッフ3人でこのスタジオを回しています。彼らは自分と全く異なるタイプなので、自分が聴かない音楽や違う意見が常に隣にある。バックグランドが違いながらも、とても鋭い感覚があるので、お互いに作ったものをボロクソに言っています(笑)。でもどこか染み付いて共有されているところがあるので面白いことが起きるんです。今はもう音楽制作だけでも仕事が埋まるんですが、やはり自分はトップ・ベースプレイヤーで在りたい。それでもやっぱり制作でも面白いことをずっとやっていたいという、自分のわがままを実現できるのはこのチームのおかげです。由紀さおりさんや、乃木坂46やアイドルもの、R&Bものまで幅広く声を掛けていただけるのはこの面白い環境を保っていられるからだと思っています。

コマーシャルやアニメやドラマのサウンドトラック、最近では、NHKのドラマ”やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる”の劇判をやらせていただいています。試写会での評判が良くその方面の仕事も増えています。自分の強みであるアコースティックなところを求められる仕事もそれはそれで楽しいんですが、台本をもらって監督と話をして、ここにこういう音楽がほしいと言われて作るのは得意。ベースを弾くときもただ曲をなぞるだけじゃなく、アンサンブルが作品として良いものなるようにイメージを俯瞰して音を入れて行くので、自分のプレーヤーとしてのスタイルにも似ていると感じています。いろんなジャンルの音楽を支える為に、いろんな曲を弾けなければいけない、知らなければいけない、ということを本当にたくさんやってきたので、培ってきたものをBGMとしてアウトプットしていくことは楽しいですね。
ウッドベースの音響再現で一番大事なのはリッチな中高域です。ベースと言う固定概念がそうさせるのかブーストされるのは低音になることが多いですし、コントラバスの音は太くあたたかく、というイメージが先行されるとそれが中低域になる。実際のところ、低音なんてものはベースという楽器を使っていれば何であっても出ます。コントラバスに大事な中高域は、ライブやレコーディングではピーキーな部分として削られることが多い。でもそこがピーキーになるかどうかは弾き方や機材の問題で、その部分をイコライザーでどうにかされるともうコントラバスである必要がなくなる。例えばポップスで処理されるような音になるならフレットレスベースでもいいし、打ち込みでもいい。でも僕は、ウッドベースのプレーヤーなので本物ウッドベースの音を届けられるということを自分の武器にしたい。そこはエンジニアだったり、ギアだったりの手助けがないとできないことなんです。特にライブでウッドベースを再現するのは相当難しく、すぐ高域をあげて、干渉する低域をカットして・・・、とせざるを得ない。正直、それまでテレビから聴こえてくる自分の音はいつも、こういう処理をされてしまったのかとか、これじゃただのラインの音じゃん、とガッカリさせられることばかりでした。Nadineは、いままでのマイクやピックアップだとカットするしかなかった中高域が出せる。外音にクオリティーの高い中高域を任せられるNadineはとてもライブに向いているマイクだなと思いましたし、実際、コントラバスらしい指先の感じがとてもクリアに聴こえます。レコーディングの時には他のマイクとも合わせやすくて、僕はリボンマイクと組み合わせて使っているし、スタジオによくあるNeumann U87との相性も良い。ただコントラバスの中高域は、楽器をちゃんと鳴らせる人じゃないとカリカリな音になってしまいますから、Nadineを使うと演奏にごまかしが効かないというシビアな側面もあります。逆にいうと、これからのコントラバスプレーヤーにとっては、気づきにもなってくれるということですね。

クラウス・シュトールという、すばらしいベルリンフィルの首席コントラバス奏者の方がいて、ある日テレビで、皇后様とラフマノフのヴォーカリーゼをふたりで演奏しているのを偶然見ていたんです。そのウッドベースの音がテレビ越しに聴いてもすごくよかった。もちろん当時はまだNadineにも出会っていなかったし、ニュースで報じられているのを見ただけなのでコントラバスにそんな特殊な処理がされている訳もない。こういういい音が出る楽器があるのかと覚えていたんです。そのあと彼はすぐ引退をして、そのまた一週間くらいした後、コントラバスのテックの方からすごくいい楽器が入ったから今すぐ来てよ!と、電話が掛かってきて見に行ったらテレビで見たその楽器だったんです。わあ、あれだ!と思って弾くとやっぱりすごい音で。値段も聞かず買いますって言ったら、外車が3台くらい買える金額でした。(笑)これが払えないようであれば俺はコントラバスプレーヤーとして選ばれてないんだろうと覚悟をしましたけどね。作家の名前は、アントニオ・ペリゾン。1700年代後期に数本しか作られていなかったもので図鑑にも載っています。まさか僕にハウスのトラックとかで使われるようになるとは思わなかったでしょうね。(笑)
誤解を覚悟でいうと無駄な練習をしなくてよくなりました。練習には基礎の練習と自分の出したい音を出せるようにする練習があります。コントラバス奏者だったら自分の理想の音があって、あーでもない、こーでもないと、弾き方、セッティング、マイク、弦、アンプとあれこれ研究をするんですが、そういう時間が全く必要なくなりました。そのおかげで時間を制作に当てられる。アイディアに使える時間ができる。簡単にいうと、以前、一生懸命出していた音が鼻くそほじりながら出せるんです。(笑)楽器が助けてくれるのでフィジカルもすごく楽になりました。やはりクラシックの方が弾いていた楽器なので、弓の鳴りもすごくよくて楽器が弓の弾き方を教えてくれます。楽器を変えただけで、弓の扱いは数段レベルが上がりました。これは“弘法筆を選ぶ”だなと。(笑)
音で判断しているプロの方には音ですぐに理解してもらえますね。”こんな音を出せるコントラバス奏者を聞いたことがない“と言われますし、エンジニアさんからは”こんないい音でコントラバスが録れたことない”といただくこともあります。イタリアの1700年製ということで喜んでくれるクライアントもいます。(笑)この楽器に出会って金額以上の価値がこの5年間でありました。自分が納得したものなら取りもどせると思いますし、ダメなら選ばれなかったというしかない。
Nadineとの組み合わせは、エレクトロトラックの中でもコントラバスらしさを保ちながら埋もれない音でムチっと録れるので、僕が目指すエレクトロとアコースティックの融合にとても役に立ってくれます。日本独特のカテゴライズ至上主義の価値観では、ウッドベースがあればジャズと思ってくれるところがあります。エレクトロなトラックにウッドベースをのせるだけで、”ジャジーですね”と返ってくる。でもやってることは全然ジャジーじゃない。(笑)否定的にそれを嘆くこともできるけど、それもひとつの取っ掛かりと思いますし、コントラバスをジャズのアイコンとしてうまく利用すればもっと面白いことができる。そこで一番で大事なのは、音色。クリスチャン・マクブライドがすごいのは、みんなテクニックの話をしますけど、ボーンという一音の凄さにあります。お金を稼ぐ音をしている(笑)。そこにキングたる所以があります。そういうところにもっと耳がいってほしいですし、僕自身も本物のコントラバスサウンドを武器に様々な業界に挑戦していきたいと思っています。
川村竜
http://www.ryukawamura.com/