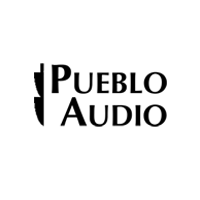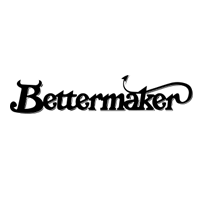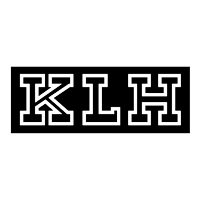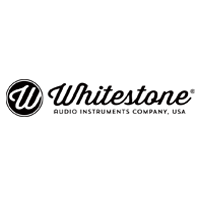LEARN - S5X
サウンド・エンジニア、ZAK
徹底したリサーチと厳密な計測に基づくサウンド・エンジニア専用ヘッドフォンを供給している「OLLO Audio」より、最新モデル「S5X」がリリースされています。従来のステレオ・ミキシング/マスタリングだけでなく、新時代のイマージブ・プロダクションを見据えて開発されたという「S5X」をいち早く導入しているサウンド・エンジニア、ZAK氏に、その製品インプレッションと、「S5X」を使ってミキシングされたという世界約30の国と地域で配信された坂本龍一氏のオンライン・コンサート「Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022」の制作について伺いました。
立体音響の作品が増えてきているので、このスタジオをドルビー・アトモスに対応させて、自分が手がけている作品を立体音響にできたら面白いのではないかと思い立ち、9.1.4のセットアップを進めているところです。9.1.4は、「Neumann KH80 DSP」と「KH 740 DSP」」サブ・ウーファーで組んで、「Trinnov MC Processor」で、発音タイミングの心配なく鳴るようにキャリブレーション調整しています。立体的な音は、ステレオ(2ch)ミックスであっても作れますが、その延長としてスピーカーが増えた時にどのような表現ができるのかという興味が先にあって、まずは自分も参加して、作品を作ってみたいという感じです。
マルチ・スピーカーは、特性を大きく使うとトリッキーに聞こえてしまうし、ギミックが前に聞こえてしまうとあまり意味がありません。空間で音が鳴っているというライブ感が大事で、体全体で感じられるものを作ろうと考えています。ドルビー・アトモス作品の制作はこれからですが、古くは89年から劇団の音響で地上4ch、天井4chの8chミックスを行なっています。自分が手がけてきた野外演劇や大きな舞台では、むしろ2chであることがなく、スピーカーの配置は、「空間にどのように音を配置したら面白いのか」を考えて劇場に対し自由に組むことができます。これまで5.1のサラウンド・ミックスも行なってきましたが、それを踏まえた上では物足りなかった。僕の中では、ようやく立体音響がフォーマットとして確立してきたという感があるのでこれに乗った方が面白いですし、これからの作品作りをとても楽しみにしています。

日本ではFOHからレコーディングまで全部行うエンジニアはまだまだ少ないですね。ライブ・ミックスは、スタジオ・ミックスと違い一度きりでスピード感が違いますし、空間の抗えない状態の中でどこまでできるのかという難しさと面白さがあります。例えば、ライブで起きた危うい状態や緊張感がどうなってそうなったかをスタジオ・ミックスで再現してみたりするんです。あの時の不安は?高揚感は?どういう音の状態だったのかの記憶を頼りにそれをスタジオ・ミックスに反映させていきます。記憶というのは曖昧なので自然と実際のライブであったり、子供の頃から聴いているクラシックのレコードの音だったりが応用、転換されていきます。音色は特にファンタジーの要素が強いと思いますし、音の質感に関しては映画の影響もあるように感じています。あまり理屈ではないですが、現実のスピーカーから鳴っているアコースティック含めた空間の音と頭の中の記憶の音が合わさったものがそもそも自分のミックスなんじゃないかと思います。そういう意味ではこれまでのステレオからドルビー・アトモスにフォーマットが移っていっても何かミックスのコンセプトそのものが大きく変わるというわけでもないかもしれません。
ミックスを行う際のヴィションはあらかじめ明確にあってそれに沿うように作っていきます。ただ脳内のイメージをそのままミックスに表現しようとすると通常のバランスとの関係がなくなり、時に独特と言われることもあります。他の人がどう考えてミキシングを行なっているかは検討もつかないですけど、フォーマット、機材、プラグインなどが変わっても自分がミックスする限りにおいては自分というフィルタが入りますし、最終のアウトプットは誰にも似ていない方が面白いものです。均一で上手なミックスは工業製品にはよいですが、それらが芸術作品になりえるかどうかは分かりません。表現は全く自由で好きに作ればよいし、結局は、まず自分自身が気持ちいいかどうかです。立体音響のコンテンツには、まだまだ可能性があると思っているので喜んでもらえる面白い作品を作りたいと思っています。

ものすごくフラットなのではないでしょうか。いままで聴いた中でもかなりフラットな特性で、聴こえてくる音が非常に正確です。低音がヘッドフォン的な鳴り方というより、若干スピーカー寄りに鳴ってくれていることで長時間使っても疲れないですね。既存の「S4X」も、とてもよくできたヘッドフォンだと思いましたけど、フラット・レスポンスをモニターのゴールと考えた場合、「S5X」を知った後では「S4X」はまだ過渡期だったのかなという感じすらします。「S4X」が(7/10)点だとすると、「S5X」は、いきなり(10/10)満点に飛躍したくらいの印象があり、悪いところが全く見受けられず開発者の執念のようなものを感じました。それぞれ耳の形が違うので個人差はあると思いますが、これでミックスしたものが他でおかしく聞こえるということはまず起き得ないでしょう。

まず今は世の中の人が音楽を聴くときの多くにヘッドフォン/イヤフォンを使っています。自分自身も外出するときにはBLUETOOTHのイヤフォンで音楽を聴きますし、ヘッドフォン・リスニングは没入できて、音楽の細部まで聴くことができるので音楽鑑賞の手段として面白いと思っています。ですから、ヘッドフォンでミックスをする意味は、ヘッドフォンで聴いたときのパンの位置の確認や、EQのレイヤーなど、細部をチェックすることもありますが、何よりヘッドフォンでクリティカル・リスニングをする人達が聴いても楽しめる作品にするためと考えて使っています。ヘッドフォンとスピーカーは違う空間で鳴るものなので同じにはなり得ないですから、別人に聞こえるようなことさえなければ多少差異があっても問題ないと思います。ミックスの際もヘッドフォンとスピーカーを行き来して、こう違って聞こえるのかと自分でも楽しんでやっていますね。ただ、ミックスは、スピーカーから始めた方が良いと考えている派で、ヘッドフォンでのモニタリングはその後です。スピーカーから作ると耳からだけの情報ではなく体感に届く音を聞くことによってそのフィードバックが生まれ、ミックスの生命力が変わってきます。これはかなり重要な要素で、ここでヘッドフォンでのクリティカルなリスニングは必要としません。但し、その後にヘッドフォンが入ることでより進んだミックスができるのは確かです。ヘッドフォンで聴かないと分からないこともありますし、見つけられないところが見つけられてこんな可能性があるんだという発見がある。細かいEQや音の重なりなどの微調整ができるのでヘッドフォンでの作業は楽しいですし、この過程は決して悪い方には作用しません。ここで扱われる「S5X」は、どこかの帯域が見えにくいとかのストレスが一切ありませんし、何よりその結果に信頼があります。

FOHの現場にも「S5X」を持って行ってミックスしてみましたがとてもよかったです。ライブではスタジオと違ってヘッドフォンからミックスを始めます。ライブの会場は混沌としていることもあるので、むしろPAスピーカーからの出音だけだと状態が分からないことが多い。「S5X」は、オープン型なのでリハーサルが始まったら表のスピーカーの音を止めて、数曲のうちにミックスの土台をヘッドフォンで作ってしまいます。「S5X」は本当に正確なので、ここで作った音を表のPAスピーカーで鳴らしても違和感がありません。イヤホンや密閉型ヘッドフォンは、ライブの最中に聞くことができますが、外音と違ってしまうのでこのような使い方はできないんです。道具の使い方は、型や技があった方が簡単で楽な時もありますが、手法に制約はないのでより良い結果を求めてなんでもやってみた方がよいと思っています。
12月11日に行われた「Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022」のミックスで行われた各曲の細かい低音調整は、ほぼ全て「S5X」で制御しました。これは坂本龍一さんが闘病中でコンサートを通しての演奏が行えないため、もっとも響きを気に入っているNHK 509スタジオで一曲ずつ事前収録したものを繋げて配信する形が取られたオンライン・コンサートです。坂本さん自身が「みんなの前で演奏できるのが最後かもしれない」として臨んだプロジェクトで、まさにプロフェッショナリズムが必要になると思いましたし、命懸けで仕事を全うしよう、頑張ろうと臨みました。
最初は映像の撮影とあわせてシンプルなイメージということだったのでスタジオ内にマイクを2本だけを立てて録ることも考えましたが、相手はピアノ一台、出来る限りしっかり録音しようとマイキングを考えました。クローズド・マイクに、ベルリンの真空管マイク「Mybugh M1」をLOW、MID、HIGH、TAILに4本。少し離れたところに硬質でクリアなサウンドのコンデンサーマイク「SONY 100N」のペアをカーディオイドで設置し、その延長上のもっと高いところに同じく「SONY 100N」ペアを無指向で立てています。レコーディングの初日に、クローズドの4本セットが「Myburgh M1」になるパターンと、「SONY 100N」になるパターンをセッティングして、坂本さんに聴いて選んでもらい決めました。「Myburgh M1」は普段「Pueblo Audio JR Preamp」で受けていますが、今回は509スタジオの「API Vision」コンソールを介して録音することになり、音が落ち着きすぎてしまうので、より輪郭が立つプリアンプ「Neumann V402」を使って「SONY 100N」の方を「Pueblo Audio JR Preamp」で受けて録っています。「V402」で見える輪郭を、面で出てくる「JR Preamp」を背景にして囲ってあげるようなサウンドのイメージで、結果的にこの二つのプリアンプは“黄金の組み合わせ”と言えるほどよく機能しました。
高さ4mくらいのところにホール・マイクに近いアンビエンス・マイクを、円を等分割した箇所に12本立てています。これらは同じマイクではなく、「Neumann M50」、「M49」、「M150」、「Schopes 64v」が混ざっています。考え方としては、ピアノに向かってLCR/SL/SR5本と反対側からのLCR/SL/SR5本、そこにLLとRRを共有する両サイドを1本ずつ、まさにサラウンド・スピーカーの位置をマイクに置き換え、それらが連続して繋がるような置き方をしています。ピアノに向かってメインになるLCR 3本には、「Neumann M50」を立て、これらは「Pueblo Audio JR Preamp」で受けています。その他のマイクは「API Vision」のHAで受けつつ、全てのチャンネルはコンソールのフェーダーを通って各ダイレクト・アウトからマスタークロック「Abendrot Everest 701A」でロックした「Avid Pro Tools」に録音しています。「Everest 701A」を入れると、湧いている水の種類が違うというか、原音に忠実なまま録音できて機械の音もフラットに聞こえるようになります。音量もあげてもうるさくならないですし、入れ物が大きいというか、全体の余裕がものすごいので音にまったくストレスが起きません。録音されたトラックには変なピークがなくそれに対するEQも必要なくなるというアドバンテージもあります。
このオンライン・コンサートは配信の他に町田の映画館でも同じタイミングで上映されていて、ミックス・ダウンは、この劇場用の5.1サラウンドをメインに作っています。配信に使われたステレオ・ミックスは、この5.1chミックスから違和感ないように作り直したものになります。5.1chミックスでは、フロントとリアに立てたアンビエント・マイクをそのまま存在させて、それ以外のバランスや距離感を曲に合わせて変えています。前もって坂本さんと話した時には、通して変化の少ないフラットな感じでも良いという感じでしたが、曲によって映像に合わせて少しずつミックスが変わっていく様を聴いてもらったら気に入っていただけました。
映画用のMAに行ったときに、ピアノでこんなにサブ・ローが入っているのを初めて聴きましたと言われて、“やめましょうか?”と答えたら、“それがいいです”と言われたので安心しました。(笑)実際、低音処理されたサウンドは評判がよくて、配信のすぐ後に知り合いのミュージシャン達から連絡があって話題に上がりました。これは先の記憶とファンタジーの話で、僕が聴いている坂本さんのピアノの音は実際にああいう鳴り方をしているんです。坂本さんの独特なトーンとピアノ本体が鳴って染み渡る音の感じを伝えたくて、ミックスでそのイメージを代弁するような効果として表現しています。このピアノの低音感は主にHIGHとLOWの「Myburgh M1」に入っている近接効果を「Manultec Orca Bay」のLOWバンドをブーストすることで作っています。「Manultec Orca Bay」は、大きなレンジを捉えられるモダンなステレオ・パッシブ・イコライザーで、箱っぽくなりがちなピアノに使っても自然な形を作ることができます。このEQで一番驚いたのはHIGHバンドをブーストすると高域が上がるのではなくピアノが木材と金属でアクションしている感じが明瞭になることでした。PULTEC EQのフィロソフィーを受け継いでいるEQなのでプラグインや他のアウトボードで同様の感じの再現を試みたんですが、生演奏が入力されて地続きで出力されていくこの特有の感じはどうやっても作ることが出きませんでした。

「Clarity」を大事にしたいという言葉を貰っていたので、録音では、フラット、ニュートラル、正確さを意識して、ミックスでは、低音の容積を確保しながらも透明度や明晰さが高く保たれたものになるように処理をしています。今回のミックスは、とてつもなく重たいものになることは目に見えていましたが、同時に何か細胞が震えるような、生きる希望のようなものを感じてもらいたいと思いました。マイクは坂本さんの耳ではないので頭の中を覗き込むようにしてお互いに共有できるところを確認するように進めました。エンジニアを任せられるからには、アーティストが求めているものを叶えたいですし、喜んでもらいたく、驚いてもらいたく、安心もしてもらいたい、そして、それをみんなにも伝えたい。簡単ではないこともたくさんありましたが、最終的にこの機会でしか残せない音を聴いてもらうことができたのではないかと思っています。
ZAK - SOUND ENGINEER, PRODUCER, REMIXER
音楽、映画音楽制作、演劇など「音」「音響」にまつわる多岐に渡る事に携わっている。忌野清志郎、菅野ようこ、坂本龍一、相対性理論、水曜日のカンパネラ、原田郁子、三宅純、ALVA NOTO、BRIAN ENO、BOREDOMS、BUFFALO DAUGHTER、FISHMANS、SUGIZO、OPN、SQUARE PUSHER、UA、YELLOW MONKEYなどの録音、MIXやLIVE PA。映画音楽監督としてはおもに豊田利晃、ワン・イェミン、犬堂一心などの作品。村上たかしとは2000年に開催された「SUPER FLAT展」以降様々な形で共同作業をしている。舞台は野外演劇を得意とする「維新派」を20年以上、飴屋法水「4.48サイコシス」「じめん」「いりくちでくち」、マームとジプシー「COCOON I & II」、NODA MAP「贋作 桜の森の満開の下」などの舞台音響を担当。直近の作品は、坂本龍一 「12」「PTP2022」など 。